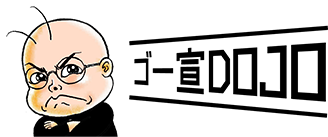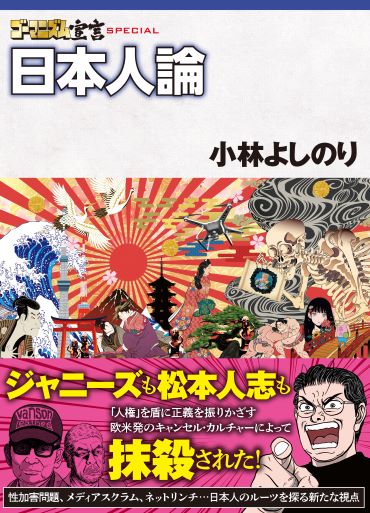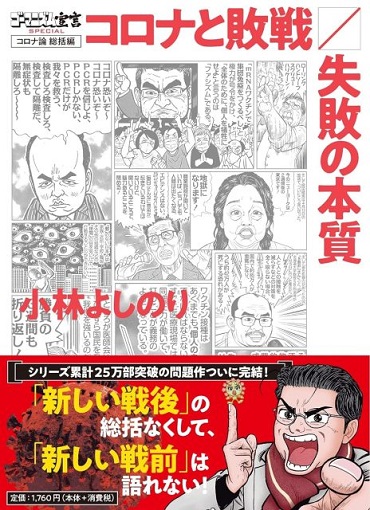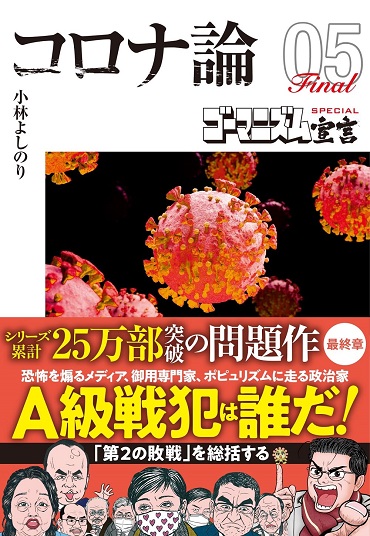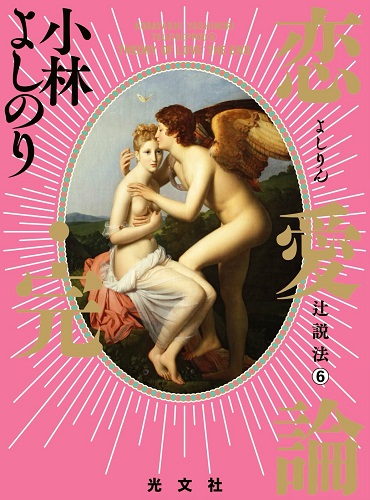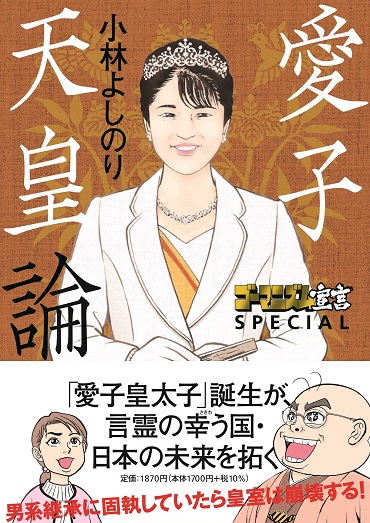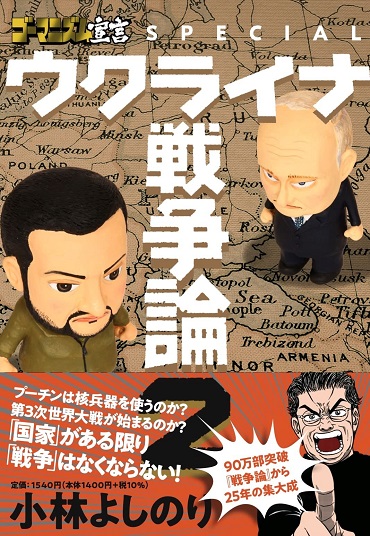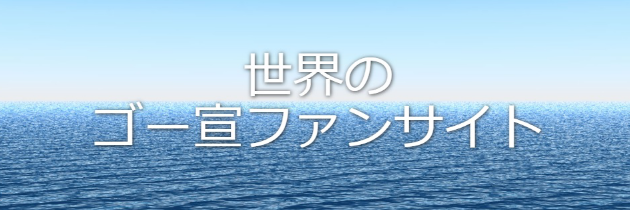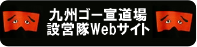憲法の政教分離原則については、いまだに誤解が多いようだ。
関係条文は以下の通り。
「第20条
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、
便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは
博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」
先ず、20条2項の「宗教上の行為…」と3項の「宗教的活動」を無造作に
同一視してはならない。
後者は「宗教教育(特定宗教の教義を褒め称えたり、他の宗教を排斥
するような教育)その他」と例示されているように、「宗教上の行為」
一般ではない。
それらの中でも“より”積極的な「活動」を限定的に指していると理解できる。
具体的には「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、
助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」(最高裁判決、昭和52年
7月13日)だろう。そのような「宗教的活動」を「国及びその機関」が行うことは憲法が
禁止している。
このこと自体に違和感を覚える国民はさほど多くないはずだ。
しかし、前者については特に禁止していない。
ただ、参加への「強制」を禁止しているに過ぎない。
現にこれまで、宮中三殿で行われる皇太子のご婚儀が国の儀式として
行われたり、衆議院・参議院葬などが普通に神式又は仏式で行われたり
してきた実例がある。
それらへの参列を強制することだけを憲法は禁止しているのだ。大嘗祭の場合は、政教分離とは関わりなく国事行為として行われるのは
相応しくない。
何故なら、国事行為の場合は法的に「内閣の意思」による行為と
見なされるからだ。
大嘗祭は、天皇陛下ご自身のお気持ちでなされることにこそ、
大切な意味がある。
皇室の行事としてなされる場合は、国の「機関」としての行為ではない。
ならば、20条3項の適用は受けない。
しかも大嘗祭の内容は、神道の祭りだから2項の「宗教上の…儀式」
ではあっても、3項の「宗教的活動」には当たらない。
公的な性格を持つ宮廷費が支出されることについても、憲法が皇位の
「世襲」継承を規定している以上、その継承に必ず伴うべきものと
観念されてきた一連の伝統的な儀式は、憲法が当然、予想し、皇位の継承を
十全たらしめる為にむしろ要請していると理解できるので、何ら問題にならない。法隆寺や東大寺など仏教施設にも従来、国費が支出されてきた。
それは、仏教の礼拝施設を荘厳ならしめる為ではなく、もっぱら貴重な
文化財を保護する観点からなされるものだ。
よって、政教分離には抵触しないとされてきた。
大嘗祭についても、神道の行事を援助するのではなく、もっぱら皇位継承に
伴うべき伝統的儀式の遂行に万全を期す為に他ならない。大嘗祭に公費を支出することは、政教分離との関わりで問題とすべき
余地はない(そもそも皇室が89条の「宗教上の組織若しくは団体」に
当たらないのは言うまでもない)。
大嘗祭が元々、国家的・公共的・国民的な性格を強く持つことは拙著
『天皇と国民をつなぐ大嘗祭』参照。なお、天皇のお手元金とされる内廷費は、毎年支出先がほぼ決まっている上、
(非現実的だが)もし全額を当てても、大嘗祭を行うには到底足りない。
だからと言って、内廷費を増額するには皇室経済法施行法の改正を必要とする
(大嘗祭が行われた翌年から減額するにも勿論、法律改正が必要)。
大嘗祭そのものを取り止めるならばともかく(もとよりあり得ないが)、
内廷費を当てるという議論はおよそ現実味を持たない。それよりも、政教分離を取り上げるのであれば、もっと別に深刻な問題が
あるのではないか。
20条1項後段の「いかなる宗教団体も…政治上の権力を行使してはならない」
との規定。
創価学会という「宗教団体」を背景に持つ公明党が政権与党の座にいることは、
これに違反しないのか、どうか。
そちらの方がよっぽど気になる。
メディアも何故取り上げないのだろうか。【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/
BLOGブログ
前の記事へ読売新聞「即位儀式考」
サウジアラビア王家の悩み次の記事へ